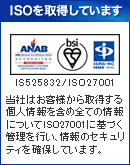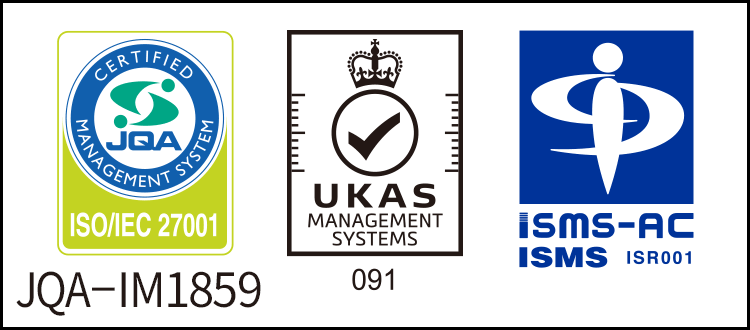賢い生命保険の選び方保険に関する税務メリット |
||
| |加入のポイント|月々の負担を軽くする|保険に関する税務メリット|基礎知識| | ||
2:満期保険金にかかる税金
養老保険や貯蓄保険などの満期保険金は受け取り時に税金がかかります。その税金は、契約者(保険料を払っていた人)、被保険者(保障の対象となる人)、満期保険金受取人が誰であるかによって種類が異なります。(下表参照)
| 契約者 | 被保険者 | 満期保険金 受取人 |
税金の種類 | |
|---|---|---|---|---|
| A(夫) | A(夫) | A(夫) | 所得税・住民税 または20%源泉分離課税 |
(例1) |
| A(夫) | B(妻) | A(夫) | (例2) | |
| A(夫) | A(夫) | B(妻) | 贈与税 | (例3) |
| A(夫) | B(妻) | B(妻) | ||
| A(夫) | B(妻) | C(子) |
■例1(*1)
「養老保険が満期になり500万円の満期金を受け取りました。夫の死亡保障で、保険料を払ったのも受け取ったのも夫です。税金はどうなりますか?」
夫が自分の保障として加入し、保険料を払い、満期保険金を自分で受け取ったケースですから
契約者:夫 被保険者:夫 満期保険金受取人:夫
となり一時所得として「所得税・住民税」がかかります。
一時所得の課税対象額は以下の計算式で求められます。
(満期保険金 - 払込保険料総額 - 特別控除額(50万円)) ÷ 2
- 満期保険金:500万円
- 払込保険料総額:200万円
- 特別控除額:50万円
(500万円 – 200万円 – 50万円) ÷ 2 = 125万円(一時所得の課税対象額)
この金額が給与などの所得と合算され、総所得に基づき所得税・住民税が課税されます。
■例2(*2)
「夫が保険料を払い、私(妻)の死亡保障として、5年満期の一時払い養老保険に入っていました。保険料は190万円で、満期になり夫が200万円受け取る予定です。税金はどうなりますか?」
夫が妻の保障として加入し、保険料を払い、満期保険金を自分で受け取ったケースですから
契約者:夫 被保険者:妻 満期保険金受取人:夫
となり「20.315%の源泉分離課税」がかかります。
銀行の定期のような「金融類似商品」には20.315%の源泉分離課税がかかりますが、生命保険も保険期間が5年以下などの条件の商品は同じような課税のされ方になります。(20.315%の内、15.315%が所得税、5%が地方税です。)
満期で受け取った200万円と保険料の差額の10万円に対して20.315%ですので20,315円を税金として収めることになります。
そのため、実際に保険会社から満期金として受け取るのは、残りの1,979,685円です。
■例3(*3)
「死亡保険を夫に掛けて保険料も夫が払っていましたが、満期となり妻が300万円(配当金を含む)を受け取ることになっています。税金はどうなりますか?」
夫が自分の保障として加入し、保険料を払い、満期保険金を妻が受け取ったケースですから
契約者:夫 被保険者:夫 満期保険金受取人:妻
となり「贈与税」がかかります。
保険料をはらった夫ではなく妻が満期保険金を受け取るのですから、夫婦間とはいえ贈与となり贈与税の対象となるのです。
贈与を受けた者1人につき基礎控除は年間110万円です。
この場合
300万円(満期険金)-110万円(基礎控除)=190万円が贈与税の課税価格になります。
(*1)出典:「No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm)を加工して作成
(*2)出典:「No.4114 No.1520 金融類似商品と税金」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1520.htm)を加工して作成
(*3)出典:「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm)を加工して作成